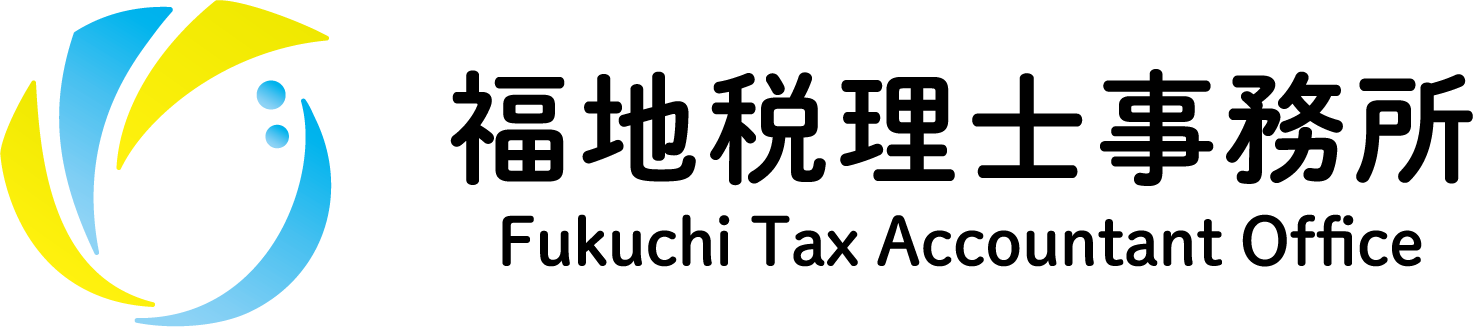こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
確定申告シーズンです。少しでも納める税金は少なく、還付される税金は多くしたいですよね。
家族を扶養にしていると「扶養控除」を受けることができます。
控除額が大きく節税効果が高いものですが、適用要件に注意が必要です。
扶養控除についてまとめてみました。
扶養控除の要件
扶養控除の適用には以下の4要件をすべて満たしている必要があります。
・配偶者以外の【親族】であること
・申告する本人と【生計が同一】であること
・扶養される人の年間の合計所得金額が【48万円以下】であること
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
これらは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡又は出国する場合はその死亡又は出国の時)の現況により判定します。
それぞれの要件の注意点
親族とは
扶養親族の親族は、「配偶者以外の6親等内の血族または3親等内の姻族」とされています。
なお、配偶者については「配偶者控除(又は配偶者特別控除)」という扶養親族とは別の控除が規定されています。
また、年齢要件があり、12月31日時点の年齢が16歳以上であることが必要です。16歳未満の場合は扶養親族ではあるものの「扶養控除」は0円です。
生計を一にする
「生計を一にする」とは、簡単に言うと同じ財布からの支出で生活しているということです。
例えば学生で一人暮らしをしているお子さんなどは、仕送りをしていれば生計一と言えます。
逆に同居していても二世帯住宅などで家計の管理がそれぞれ独立している場合は、生計は違うということになります。
所得税基本通達2-47
法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
生計が一でない家族について扶養控除を受けることはできません。
合計所得金額が年間48万円以下
実務的に一番チェックされるのはこの収入要件です。
合計所得金額が年間48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)は、給与収入では103万円以下となります。
いわゆる「103万円の壁」というヤツですね。
1円でも超えているとアウト。所得が高い人は税率も高く、扶養控除を受けられないことによる影響も大きくなります。
特に大学生などそれなりの年齢のお子さんについては、コミュニケーションをしっかり取っておくのが良いでしょう。
なお、令和7年から19才~22才の収入制限の改正が入る予定です。
専従者
誰かの専従者になっている人を扶養控除として適用することはできません。
なお、あまりないケースではありますが、専従者が事業主を扶養とすることは可能です。
その他の注意点
扶養を二重に取ることはできません。例えばお子さんを夫婦それぞれが扶養控除とすることはできず、いずれか一方のみの控除となります。
多くの場合、所得が高い人の扶養とした方が節税効果は高くなります。
扶養控除額
扶養控除の控除額は年齢によって以下のように定められています。
| 家族の年齢 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
|---|---|---|
| 16歳未満 | 0円 | 0円 |
| 16歳~18歳 23歳~69歳 | 38万円 | 33万円 |
| 19歳~22歳 (特定扶養親族) | 63万円 | 45万円 |
| 70歳以上※ (老人扶養親族) | 48万円 | 38万円 |
※老人扶養親族のうち直系尊属(父母・祖父母など)と同居している場合は、所得税が+10万円、住民税が+7万円、控除額が大きくなります。
まとめ
国税時代、収入要件が満たされていない誤りはとても多かったです。
後々税務署から指摘され修正となると、加算税や延滞税などのペナルティが発生する可能性があります。
扶養控除を受ける際は、適用要件によく注意しましょう。
【編集後記】
次男が胃腸炎に罹りました。
看病は大変ですが、こういう時は退職してて本当に良かったと思います。