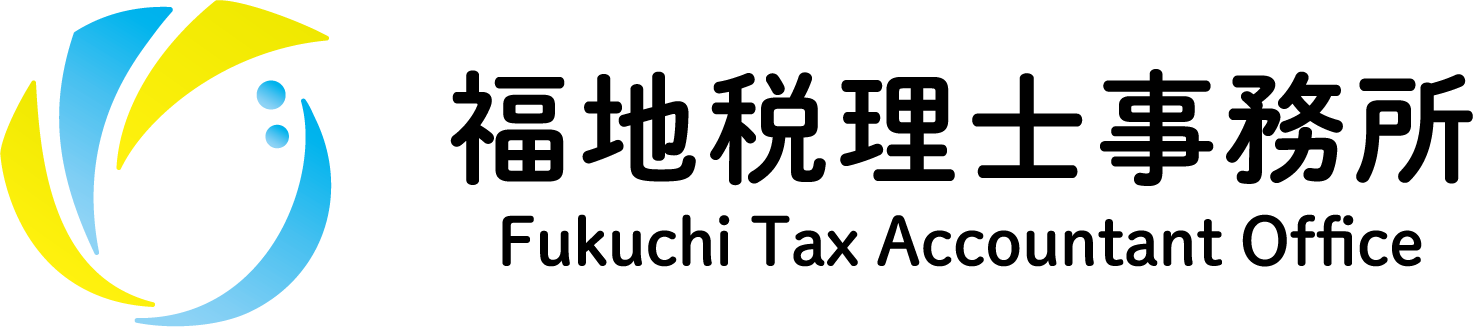こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
各仲介サイトでのポイント付与は終わってしまいましたが、それでもお得な納税。
自己負担実質2,000円で各地の特産品がもらえます。
この自己負担実質2,000円ですが、平均課税を適用している場合は若干、上がってしまうことがあります。
ふるさと納税とは
ふるさと納税制度のおさらいです。
ふるさと納税は自分の好きな自治体に寄附できます。縁もゆかりもないところでもOK。
寄附をした自治体から、金額に応じた返礼品をもらえるというのが一般的です。
寄附額から2,000円を引いた金額が所得税や住民税から控除されるため、実質的な負担は2,000円で、寄附のお礼に色々な名産品などがもらえる、というものです。
ただし、その方その方の所得に応じて限度があります。
ざっくりした計算方法は
①所得税から、(寄附額-2,000円)×税率分を控除
②住民税・基本分として、(寄附額-2,000円)×10%を控除
②住民税・特例分として、(寄附額-2,000円)×(100%-10%(住民税・基本分)-所得税の税率)
となります。
例えば令和7年分の寄附なら、①を令和7年の確定申告・ワンストップ特例で、②③を令和8年度の住民税で子所する仕組みです。
そして③の住民税・特例分について、住民税所得割の2割まで、という限度があります。
所得が高ければ高い程、住民税所得割は大きくなりますので、その分寄附できる金額も上がる、ということになります。
平均課税とは
所得税は暦年、つまり1月1日から12月31日までの所得(=儲け)を元に計算します。
また、累進課税と言って、課税される所得が高いほど税率も高くなる仕組みで(不動産譲渡や株式譲渡などの分離課税は除きます)、所得が高いほど税金の負担も大きくなります。税率は5%から45%まで段階的に上がります。
(参考:国税庁HP「所得税の税率」)
そのため、数年間で考えた場合、トータルでは同じ所得金額でも、毎年同じくらいの所得の方と、1年だけボーンと所得が上がった方では、税負担に差が生じてしまいます。
本人の意思でなく、漫画家さんの印税や自然資源に基づくもの(漁獲など)のように、自分でコントロールできないものが原因で差が生じている場合は不公平となります。この不公平な差を埋めるのが平均課税という制度で、漫画家さんの場合、原稿料や印税、著作権使用料による所得は平均課税の対象となります。
平均課税を適用すると所得税を大幅に減らせる例も多く、漫画家さんの強い味方となる制度です。
ただ、住民税には適用できず、所得税だけのものになります。
ふるさと納税と平均課税
本題の「ふるさと納税と平均課税を併用したときどうなるか」というお話です。
そもそも、「ふるさと納税と平均課税を併用できるのか?」と心配される方もいらっしゃいますが、これは問題ありません。平均課税の適用要件に「ふるさと納税をしないこと」なんてものは無く、併用は可能です。
次に住民税の限度額についてですが、こちらも特に変わりはありません。住民税に平均課税は影響しないので、所得税で適用してもしなくても限度額は変わりません。
主に影響があるのは上記計算方法の【①所得税から、(寄附額-2,000円)×税率分を控除】の部分になります。
計算が複雑なので非常にざっくりとした説明になりますが、元々所得税の税率が20%だった方が、平均課税の適用で10%に下がった、と仮定します。寄附額を302,000円とします。
すると。所得税から減額されるのは300,000円×10%=30,000円です。
②の住民税・基本分は変わらず10%なので30,000円。
③の住民税・特例分で使用する所得税率は平均課税を適用した税率でなく、元の税率になります。
そのため、300,000円×(100%-10%-20%)=210,000円
合わせて270,000円の控除となり、寄附額が302,000円ですので、実質負担は32,000円となってしまいます。
ものすごく大雑把な説明で実際の計算とは少し違うんですが、【寄附額×平均課税で下がった税率分】くらい、自己負担が上がってしまう可能性がある、とイメージするとわかり易いかと思います。
それでも平均課税をした方が得なケースが多い
上記の例では自己負担が30,000円上がってしまいましたが、平均課税を適用するとそれこそ何十万と所得税が減少することもあります。
まぁそもそもふるさと納税は返礼品の通信販売ではなく寄附ですからね・・という話は置いておいて、損得で考えても平均課税を適用した方が得になることが圧倒的に多いと思います。
返礼品も寄附総額の3割相当分もらえるわけですから、そこまで深く考えず、通常の限度額のとおりとしておけばいいんじゃないかな、というのが個人的な見解です。
終わりに
年末が近づいています。ポイントが無くなったとはいえ、これからふるさと納税をまとめてする、という方も多いと思います。
物価高が続いていて、税や社会保障の負担も重いです。ふるさと納税の是非はさておき制度としてあるわけですから、上手に活用したいところです。