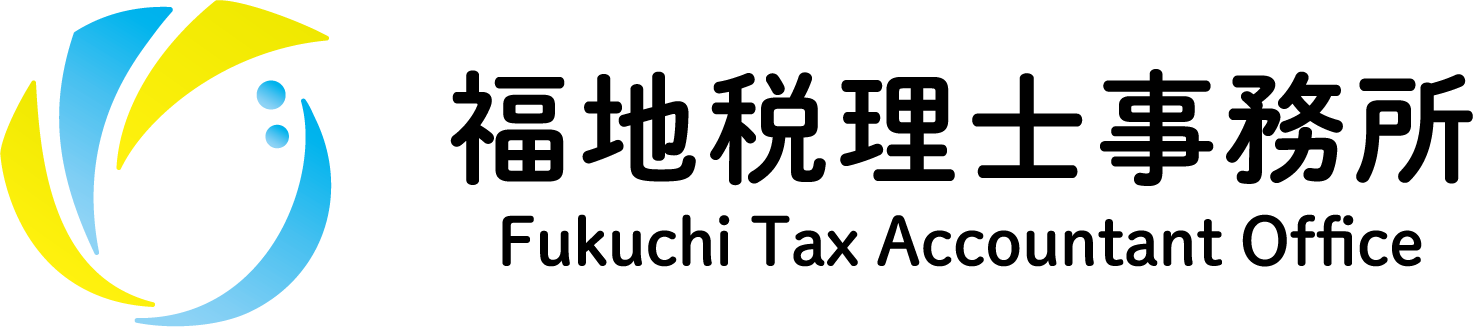こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
少し前、ふるさと納税の返礼品について最高裁での判決がありました。
ポイントは「ふるさと納税の返礼品は一時所得に該当。返礼品価値の正確な把握が必要」です。
事案の概要
主人公はとある富裕層の女性。この方、給与所得などは適切に申告していましたが、ふるさと納税の返礼品による一時所得を申告していませんでした。
2017年及び2018年(平成29年及び平成30年)の2年間で延べ約110自治体に490件、金額にしておよそ660万円のふるさと納税をしていましたが、その返礼品価値約280万円(税務署算定)について確定申告していなかったというもの。
660万円て・・。凄いな。お金持ちの方ですね。
追徴税額は40万円超になり、これを不服として最高裁まで争い、負けたようです。
ポイント1:返礼品は利益であり一時所得として課税
今回の裁判では、ふるさと納税によって受け取った返礼品は「経済的利益」であり一時所得に該当すると判断されました。返礼として得られる物品は、無償で受け取っているということで所得と判断されます。
まぁこの点は前々からそうでしたし、税務署に勤務していた時、何度も確定申告会場で「返礼品の申告に来た」という方を見ましたので、きちんと明言されたと受け止めるのが妥当でしょうか。
この返礼品をいくらで申告するのか、というのが次のポイントです。
一時所得というのは、懸賞や競馬の払戻、生命保険の満期金など、継続的でない一時的なもので労働の対価でないものを言います。
この一時所得、収入から経費を引いて、さらに特別控除50万円をひいて、残った金額に1/2を掛けて計算します。
ふるさと納税の返礼品に経費はありません(寄附はあくまで寄附であって、返礼品をもらうコストではありません)ので、価値が50万円を超えたら申告を考える必要があります。
ポイント2:返礼品価値を正確に把握するのは納税者の義務
概要に記載したとおり、寄附額660万円に対し返礼品価値は280万円となっています。
この280万円をどうやって出したかと言うと、税務署が寄附先の自治体に一件一件照会を掛け、回答を貰うというシンプルな手法で行ったもよう。
手間ひまかけてますね。それだけ本気だったということ、かなぁ。
女性側は「市場の小売価格で判定すべき」「それが無理なら総務省の言う「3割ルール」があるのだから、寄附金の3割とすべき」などと主張したようですが、いずれも退けられたとのこと。
最高裁の判断は「税務署の算定方法を支持。納税者は各自治体に調達価格を確認する義務がある」となっています。
さらには女性が「各自治体への調達価格確認は膨大な労力で現実的でない」と反論しますが(そりゃそうだと思います)、最高裁は「多大な労力であっても当然の負担である」と一蹴。
とどめに「3割ルールは税務官庁が納税者に対して公的見解を示したとは認められない」だそうです。
税務署の現場的には3割で申告しておけばいいと思います
総務省が「3割がルールだ!」と大々的に謳っていながら、片や確定申告では3割ルールではダメだ、というのはやっぱりおかしい気がしますけど・・。
あくまで個人的な見解ですが、税務署内部にいた経験からすると3割で申告しておけばまず目を付けられることはないと思います。「この3割、おかしくない?もっと価値あるでしょ」という目線で調査されることは費用対効果からしてもないんじゃないかなぁ。
この女性が狙われたのは「返礼品の申告がない(+高所得者)」なのが原因かなと思います。
終わりに
自治体も税務署からの照会であれば無視できないので回答しますが、いち納税者から返礼品の価値を聞かれても答えてくれないんじゃないかと思います。
税務署の立場からすると、返礼品の申告がない、というのは狙いやすい内容になります。逆に言えば3割で申告していればまず問題になることは無いかと。
「本当は3割を超えているだろう?」という調査だと大変な労力が必要ですからね。
ふるさと納税の返礼品、きちんと申告しておきましょう。