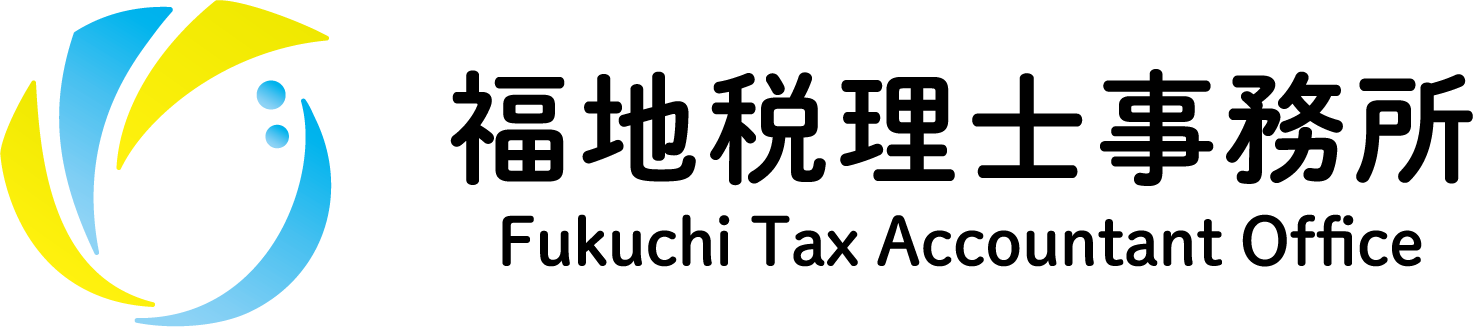こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
日に日に年末が迫っていて、確定申告も近いなぁという感じです。そのため、お客様から何件か医療費控除についてのご質問をいただくことがあります。
ということで、おさらいの意味も兼ねて申告方法などを。
医療費控除とは
医療費控除とは、簡単に言うと「かかった医療費に応じて税金が安くなる制度」です。
医療費そのものが還って来る訳ではなく、「かかった医療費に応じて税金が安くなる」という点がポイント。
会社員や公務員などの給与所得者の場合、年末調整でいったん税金の計算が終わります。年収に応じた税金が天引きされ、その金額が確定する、という訳です。天引きで税金(所得税)を払っている訳ですから、それ以上何か支払ったりする必要はありません。
医療費控除は年末調整では受けられない控除のため、確定申告での手続が必要です。
確定申告で医療費控除をした結果、年末調整で確定した税金が安くなります。既に支払が終わっている訳ですから、安くなった分が還って来る、という仕組みです。
たまーに「10万円以上医療費が掛かったらその分が還って来る」と思われている方がいらっしゃいますが、還って来るのは医療費ではなく税金です。
医療費控除の対象になる金額
医療費控除として申告できる金額がいくらになるか。
よく聞く「10万円を超えたら、その超えた部分が対象になる」という話。
これは合っているようで正確ではありません。
医療費控除として対象になる金額には足切りがあり、多くの方にとってそれは10万円になります。
しかしながら、所得の合計が200万円未満の場合、足切り額は所得の合計×5%となります。
給与所得のみ、年金所得のみの場合、所得200万円は収入ベースだと大体300万円位です。
特に年金収入のみの場合、医療費が10万円未満であっても対象となる場合は結構ありますので、「10万円行かなかったから今年はだめだ」と決めつけず、とりあえず領収書などは残して集計してみましょう。
減税額は医療費控除額×税率分
減税額は医療費控除額×税率分です。医療費控除は所得税と住民税に効果があるので、その合算した税率分になります。
所得税の税率は5%~45%まで所得に応じて段階的に上がります。これに対し、住民税は一律10%です。
仮に所得税の税率が20%、年間の医療費の支払が30万円の方の場合は、
30万円-10万円(足切り額)=20万円
20%+10%=30%(所得税と住民税の合算)
20万円×30%=6万円が減税効果となります。
対象となる医療費
対象となる医療費は簡単に言うと「治療のために必要なもの」です。目的が治療であれば、ドラックストアで購入する風邪薬なども対象になります。
一方で、予防や美容、歯列矯正などは原則対象になりません。
例えば人間ドックや栄養ドリンクなどがそれに当たります。
例外もあり、人間ドックの費用は予防目的なので対象となりませんが、疾病が見つかって引き続き治療を行う場合は、治療の一環としてOKとなります。
また、歯列矯正も大人が行う美容目的のものはNGですが、子どもはOKとされています。
ご自身の医療費の他、生計を一にする家族の分がまとめて対象になります。
上記のように控除額×税率分が減税額となるため、通常、家族内で一番収入が高い人=税率が高い人で申告すると一番効果的です。
申告方法
確定申告で医療費控除をするためには、「医療費控除の明細書」に必要事項を記入し、確定申告書に添付して提出します。
医療費の領収書やレシートは提出する必要はありません(医師の証明などは提出の必要あり)。ただし、申告後5年間は保管し、税務署から提出・提示するよう指示があったときに従う必要があります。
終わりに
年末~年始の確定申告の時期になると必ず医療費控除が話題になります。テレビであったりネットニュースであったり。
実は足切りもありそこまで大きな減税にならないことも多いんですが、身近な節税策であることに違いはなく、利用できそうであれば積極的に利用しましょう。