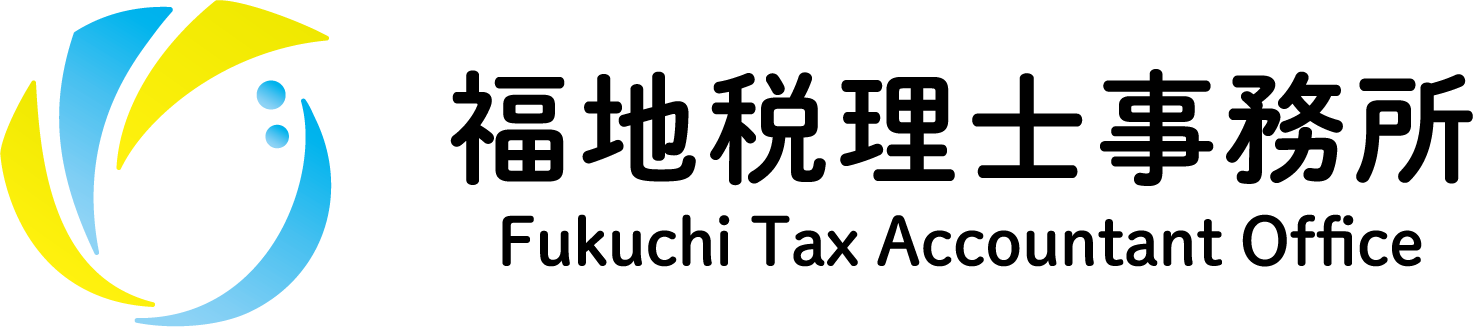こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険の保険料は確定申告の内容に基づいて決まります。
確定申告では原則として全ての所得を申告する必要がありますが、株式譲渡や配当で【特定口座・源泉徴収有口座での取引】についてはする・しないが任意となっています。
この「申告しなくていい金融所得」に対し、保険料をどうにか負担させようというのが狙いです。
前々から言われていたが・・
振り返れば岸田元首相も石破前首相も、首相就任前は金融所得課税について「強化したい」という旨の発言をされていました。
これは保険料への反映のみならず、現行の金融所得に対する税率20%を30%程度に引き上げることも視野に入れた発言であったと思います。
ところが首相に就任後は「見送りたい」「当面考えていない」など消極的な姿勢に転じ、現在に至っています。
詳しくはわかりませんが色々と事情があるんでしょう。前々からあった話ということで、それがまた再燃しているような状況です。
高齢者を中心とする富裕層の負担引き上げが狙い
「貯蓄から投資へ」の方針と逆行することになるため、税率自体の引き上げは当分されないだろうと思っています。
保険料や保険証の負担割合はどうか。
今回の狙いは「国民健康保険」「後期高齢者医療」「介護医療」の保険料へ反映させることです。
融資産はシニアの保有比率が高く、高齢富裕層がターゲットの中心でしょう。
ここで注目なのはサラリーマンや公務員など給与所得者が加入する社会保険には影響がないということです。
これは不公平感がものすごく、反発は必至でしょう。タダでさえ高い国保にさらに狙い撃ちするかのように吹っ掛けてくるとは・・。
どうなるでしょう。
終わりに
一口に「保険料に反映」と言っても実現へのハードルは高いと思われます。
おそらく配当や利子、株式譲渡に関する法定調書を活用するつもりでしょうが、これは現行、金融機関が国税庁に提出する資料で、自治体には出されません。
マイナンバーと証券口座の情報の紐づけは絶対に必要ですが、全ての情報を網羅できるんでしょうか。非上場株式の配当なんてどうやってやるんでしょう。