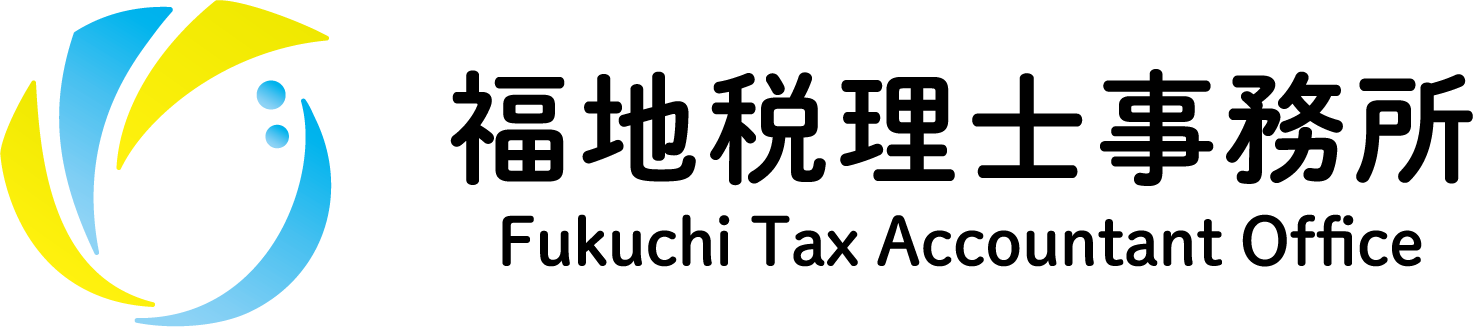こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
非居住者の方が国内において国内源泉所得に該当する退職手当等(海外赴任中に退職して退職金を受給する場合や、日本で働いていた外国人が非居住者となった後に厚生年金の脱退一時金など)を受け取る場合、20.42%の源泉徴収が行われ、原則これで課税関係が完結します(源泉分離課税方式)。
しかし、「退職所得の選択課税」制度を利用することで、全部または一部の税金の還付を受けられる可能性があります。
退職所得の選択課税とは
居住者の退職所得は給与所得などの総合課税される所得と比べ、だいぶ税額が抑えられる計算方法となっています。
これに対し非居住者は支給額に一律20.42%の税率で課税されるため、退職金を受け取る際、たまたま居住者だったか非居住者だったかによって、負担額が異なってしまいます。
このような不合理の調整のため、非居住者が受け取る退職金については、居住者と同様の税額計算を行うことが認められています。これが退職所得の選択課税です。退職所得の選択課税による税金の計算結果が源泉徴収された税額より小さい場合、その差額の還付を受けることができます。
申告書の書き方・出し方
受取った翌年1月1日(同日前に「退職所得の選択課税」の規定の適用を受ける退職手当等の総額が確定した場合には、その確定した日)以後に、一定の事項を記載した「退職所得の選択課税の申告書」を提出する必要があります。
用紙は、専用のものがないため、通常の所得税の確定申告書と第三表を利用します。
原則として非居住者であるわけですから、「納税管理人」を選任する必要があり、還付金は「納税管理人」の口座に振込まれます(再入国するなど居住者となっている場合は納税管理人は不要です)。
申告の際は、以下の点に注が必要です。
・基礎控除を含め、全ての所得控除の適用がない
・一時金以外にも退職金の支給がある場合は合算し税額計算を行う
・退職所得の選択課税(5~45%の超過累進課税)よりも源泉徴収(一律20.42%)の方が有利な場合もある
国税庁の記載例も参考にしてください
(→国税庁HP「退職所得の選択課税の記載例」)
外国人の方が受け取る「脱退一時金」
脱退一時金とは
外国人が働いている事業所が健康保険・厚生年金の適用事業所であれば、外国人であっても健康保険・厚生年金に加入します。
ですが数年で帰国するなど加入期間が短い場合、厚生年金の保険料を支払っても年金の給付を受けることができません。
そのため、保険料の掛け捨てを防ぐために、外国人(厚生年金の被保険者期間が6カ月以上ある者に限ります)が帰国後2年以内に日本年金機構に請求することにより、「脱退一時金」の支給を受けることができます。
脱退一時金は退職所得となる
この脱退一時金は、支給時に20.42%の源泉徴収が行われます(居住者であった期間に行った勤務に基因するもの国内源泉所得となるため)。
所得税法31条で、脱退一時金は退職所得とみなすと規定されています。
所得税法31条1項
次に掲げる一時金は、この法律の規定の適用については、前条第一項に規定する退職手当等とみなす。
国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法及び独立行政法人農業者年金基金法の規定に基づく一時金その他これらの法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類する制度に基づく一時金(これに類する給付を含む)で政令で定めるもの
脱退一時金も「退職所得の選択課税」により申告でき、還付を受けることができます。
まとめ
退職所得の選択課税申告書を提出することで還付が受けられる場合は、忘れずに提出するようにしましょう。
なお、通常の確定申告をする場合、退職所得の選択課税を一緒に申告してはいけません。
通常の確定申告とは別に退職所得の選択課税申告書を提出しないと、還付は止められ出し直しとなってしまいます。注意しましょう。
【編集後記】
税務署での実務では圧倒的に「脱退一時金」によるものが多かったです。
国税庁HPの確定申告書作成コーナーでは対応していないので全て手書きなので大変でした。