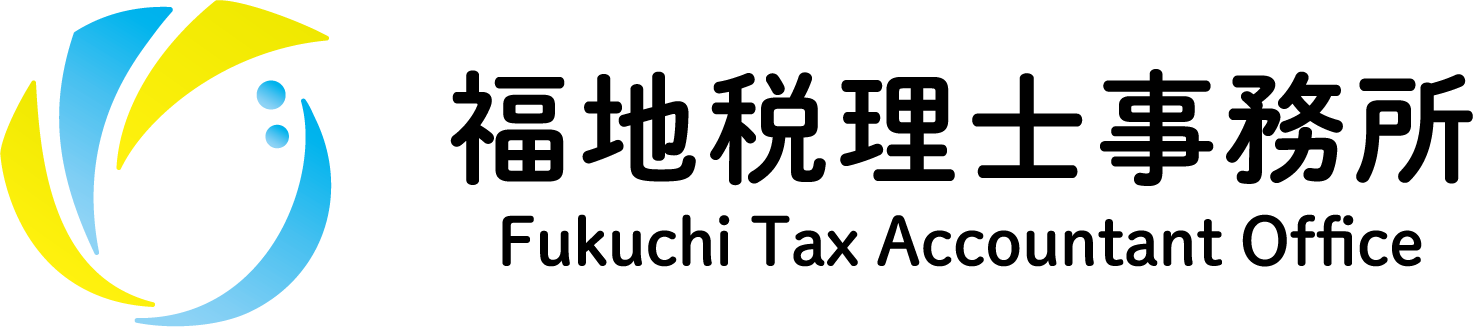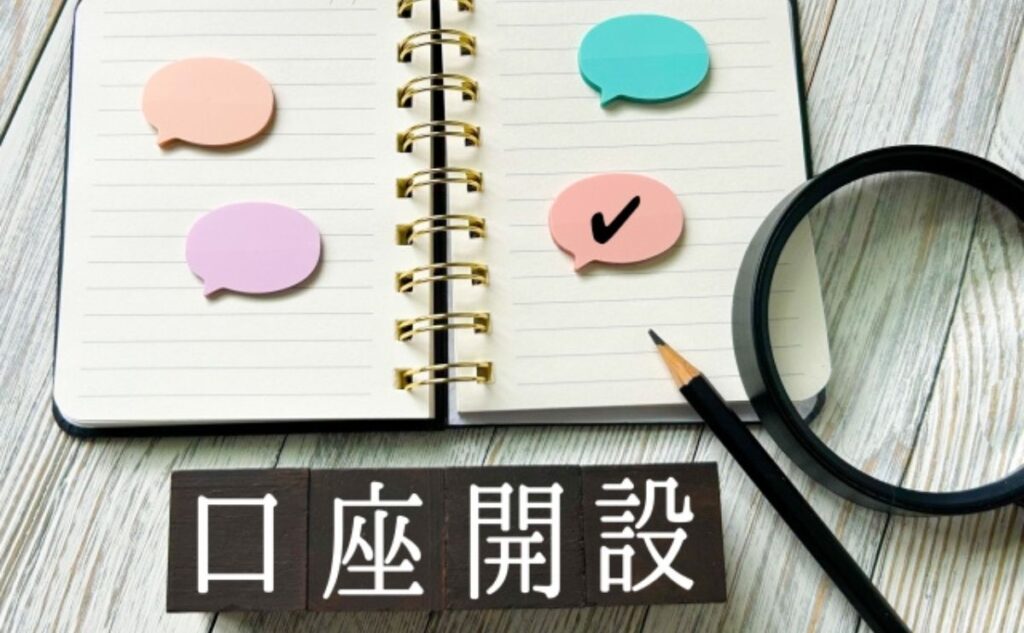
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
NISA口座の開設と共に特定口座も開設しました。というかこちらの意思とは無関係に開設となりました。
NISAは非課税で、NISAに納まらない額は特定口座か一般口座で扱うことになるため開設が必要と。
特定口座は源泉徴収あり・なしの2つ、それと一般口座と合わせ、3択です。
こういうときは特定口座・源泉ありを選びましょう。
それぞれの違い
特定口座・源泉徴収あり/なし
特定口座は金融機関や証券会社が年間の譲渡損益を計算してくれるものです。
さらに「源泉徴収あり」を選択すれば、譲渡利益や配当金に対して所得税・住民税を天引き(所得税15.315%・住民税5%の合計20.315%)して本人に代わって税務署に納めてくれます。
特定口座・源泉徴収ありの口座で得た利益はこれで課税関係を完了させ、確定申告をしなくてもいいことになっているため、手続きの手間が省けてとても楽です(確定申告しなくてもいい、なので申告してもOKです)。
特定口座・源泉徴収なしの口座の場合は、譲渡損益の計算までやってくれますが税金の手続きはしてくれません。利益が出れば多くの場合確定申告が必要となります。
一般口座
一般口座は譲渡損益の計算を自分で行うものになります。
そうなると損益が金融機関や証券会社はわからないので、当然のことながら源泉徴収はありません。
自分で譲渡損益を計算すると大変なうえ誤りや抜け漏れの危険もあります。
特定口座・源泉徴収ありを選びましょう
ということで、特に理由がなければ「特定口座・源泉徴収あり」を選びましょう。
これを選べば確定申告する・しないが選択制となります。
そのため、「計算とかめんどくさいから申告しなくていいや」が違反になりません。
ただし!一度「申告しない」を選択した後、「やっぱり申告したい」ができなくなる点には要注意(逆も同じです。申告した後、「やっぱり申告したくない」はできません)。
税務署にいたとき、毎年これで揉め事が起こっていました。
銀行員さんも大変です
この説明を銀行員さんにしてもらいましたが、銀行の窓口では職業を名乗るわけで、税理士というと非常にやりづらそうにしていました。
ごめんなさいです。